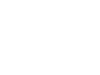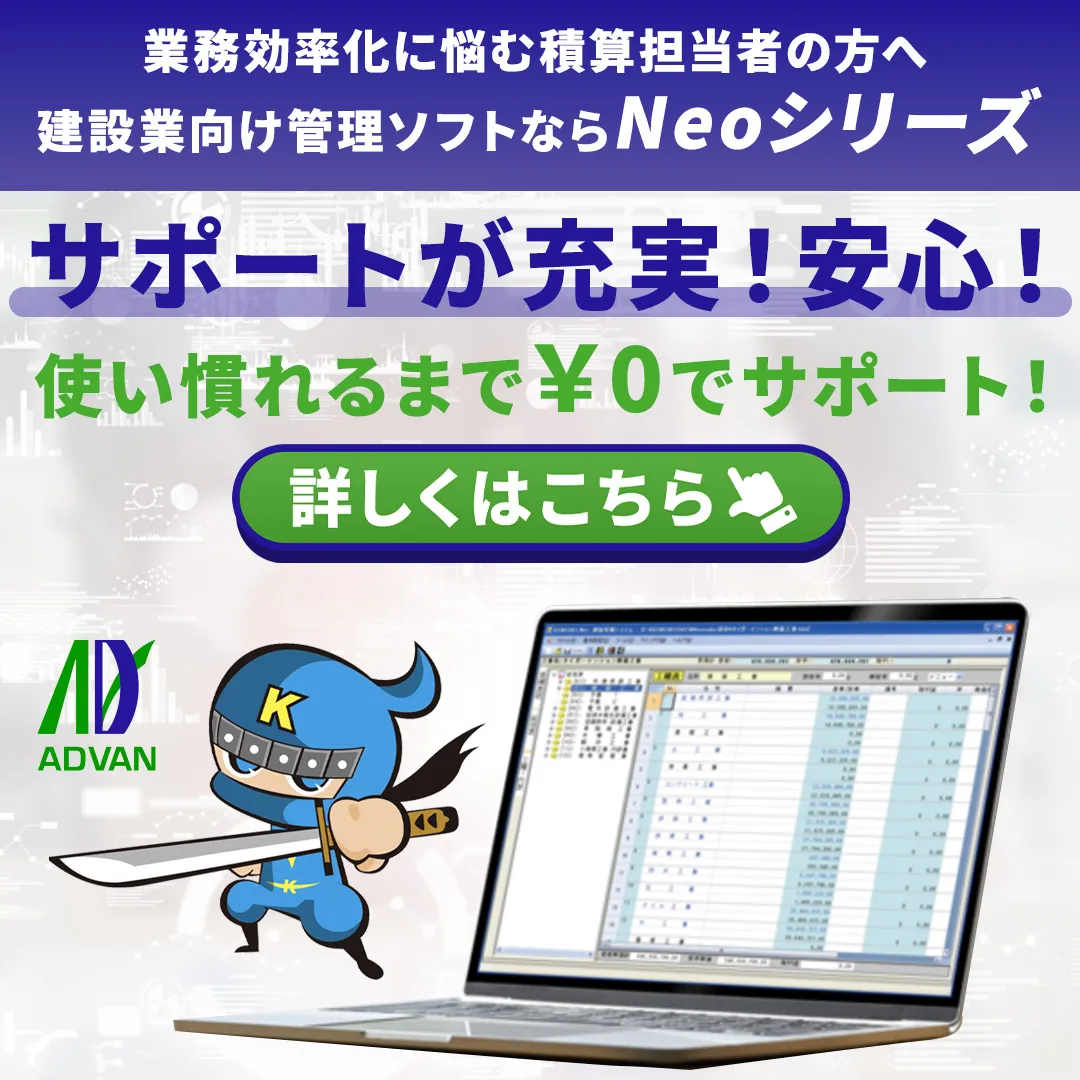見積書を発行しないと法律違反になる?押印の有無や電子見積書の効力
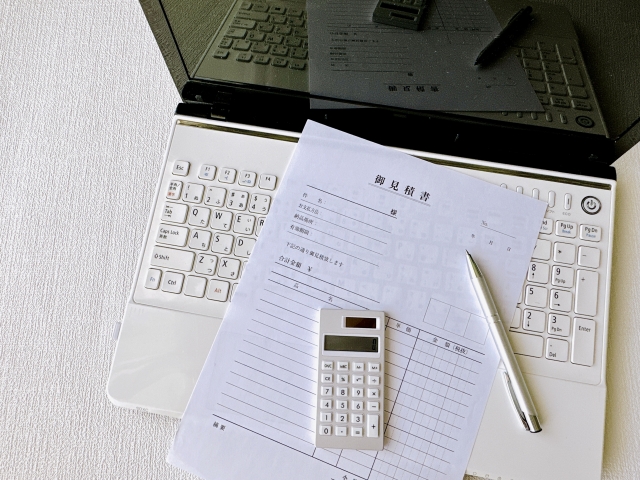
見積書は、取引の基本となる重要な書類です。しかし、見積書を発行しないと法律違反になるのか疑問に思う方もいるでしょう。
実際には、法律上の義務はありません。ただし、建設業では建設業法第20条により、見積書の提出が義務付けられています。
本記事では、見積書の役割や発行時のポイント、法的な側面について解説します。
見積書が持つ役割
見積書は単なる価格提示の書類ではなく、ビジネスにおいて重要な役割を果たします。発注者と受注者の間で認識のズレを防ぎ、円滑な契約を結ぶために不可欠です。
以下で、詳しく解説します。
相互の認識を一致させる
見積書の発行によって、取引の条件が明確になり、双方の認識を一致させられます。
たとえば、価格や納期、提供されるサービスの内容が具体的に記載されるため、契約後に「言った・言わない」といったトラブルを未然に防げるでしょう。
とくに、仕様が細かく定められる業務では、事前に見積書を発行すれば、ミスやトラブルを最小限に抑えられます。これにより、スムーズな取引が実現し、業務の効率化にもつながります。
【関連記事】建設業の業務効率化をかなえるために必要なことは?
取引の証明になる
価格の変動が頻繁に起こる業界では、過去の見積書が価格交渉の際の貴重な資料となります。
材料費や人件費が変動する業種では、過去の見積書と比較しながら、適正な価格を提示できます。
また、見積書は税務調査や監査の際にも正式な証拠に活用されることも。
税務署や監査機関に対して適切な取引を行っていると証明できるため、正しい方法で管理・保管するのが賢明です。
発注を検討してもらいやすくなる
発注者は見積書の内容を精査し、費用対効果を判断した上 で発注します。
見積書がないと、ほかの企業との比較が難しくなり、発注が遅れる可能性があります。
とくに、競争が激しい業界では、分かりやすい見積書を作成するのが大切です。
明確な情報が記載されている見積書は、取引先に安心感を与え、信頼関係の構築にも役立つでしょう。
これによって、スムーズな商談や契約締結へとつながり、ビジネスの拡大に貢献します。
見積書を発行しないと法律違反になる?
見積書の発行は、法律で義務付けられているわけではありません。
ただし、特定の業界では発行が必須な場合があるので注意が必要です。
建設業では建設業法第20条により、見積書の提出が義務付けられています。
請負契約の適正な履行を確保するために、見積書に材料費や労務費の内訳の明示を求められます。
そのほかの業界でもトラブルを防ぐために、なるべく見積書を作成し、適切な管理を行うことが望ましいです。
見積書の押印はあった方がベター
見積書には押印が必須ではありません。しかし、取引の信頼性を高めるためには、押印を行うのが一般的です。
押印があれば、見積書が正式な書類としての効力を強め、取引先に安心感を与えます。
公的機関や大手企業との取引では、押印が求められるケースが多いため、実務上は押印するのが望ましいです。
PDFで見積書を発行した際の法的効力
電子化が進む中で、PDF形式での見積書発行が増えています。
ここでは、紙の見積書とPDF形式の見積書は、同等の効力を持つのか解説します。
PDFで発行した見積書も効力は紙と同等
法律上、PDF形式の見積書も紙の見積書と同等の効力を持ちます。
近年では電子契約の普及により、PDFによる見積書が標準になりつつあります。
ただし、改ざんリスクを防ぐために、電子署名やタイムスタンプの活用がおすすめです。
電子署名を施せば、発行元の真正性を証明し、法的な有効性を強化できるでしょう。
また、タイムスタンプは、見積書が特定の時点で発行されたことの証明になるため、改ざんリスクを減らせます。
電子で見積書を発行する際の注意点
電子見積書を発行する際には、以下の注意が必要です。
- 取引先が電子見積書を受け入れるか確認
- 改ざん防止対策を講じる
一部の企業や公的機関では、紙の見積書を求められる場合があるため、取引先に確認するべきです。必要に応じて、紙の見積書を用意しましょう。
また、PDFのパスワード設定や電子署名を利用すると、より安全な見積書となります。
見積書の有効期限の必要性
見積書の有効期限は、取引をスムーズに進めるために重要です。以下では、有効期限の必要性を解説します。
一般的に記載される有効期限の目安
見積書の有効期限は業界や取引内容によって異なります。一般的には、有効期限は1週間から1ヶ月程度に設定されます。
建設業・製造業は、資材価格の変動があるため、1~2週間の短期間に設定されることが多い傾向です。
一方で、IT・ソフトウェア開発の場合は、1〜3ヶ月程度の長めの期間で設定されます。
有効期限を記載するメリット
仕入れ価格や為替レートの影響を受けやすい業界では、一定期間内の契約締結を促すことで、価格変動による損失を防げます。期限を過ぎた場合は、新たな価格で見積もりを提示できるため、適正価格を維持しやすくなるでしょう。
また、取引の意思決定が迅速化されるメリットもあります。有効期限を設けることで、発注者は決定のタイミングを意識し、契約がスムーズに進みやすくなります。
スケジュール管理のしやすさも向上するため、契約締結の遅延による影響を最小限に抑えられるのもメリットです。
さらに、契約条件の明確化できるのも魅力です。期限を設定すれば、明確な条件のもとで契約が成立しやすくなるでしょう。
有効期限を設定する際の注意点
見積書の有効期限は、短すぎても長すぎても問題が発生するため、慎重に設定する必要があります。
有効期限が短いと、発注者が社内承認を取る前に期限が切れ、契約の機会を逃す可能性があります。
とくに公的機関や大企業では、審査や稟議(りんぎ)まで時間を要するため、適度な余裕が必要です。
一方で、期限が長すぎると、価格変動や条件変更のリスクが高まります。そのため、契約時に再調整が必要になる場合があります。
有効期限を設定する際は、発注者の決定に十分な時間を確保しつつ、価格変動リスクを抑えることが大切です。
柔軟な対応ができるように、期限延長の交渉を想定しておけば、トラブルを防げます。
見積書に記載する項目
見積書には、取引内容を明確にし、トラブルを防ぐために必要な情報を記載します。以下の項目を適切に記載すれば、スムーズな契約につながります。
| 項目 | 詳細 |
| タイトル | 「御見積書」のように、見積書であることを明示する |
| 宛先 | 取引先の会社名・担当部署・担当者名を記載する |
| 発行日・提出日 | 見積書の発行日や提出日を記載し、取引時期を明確にする |
| 発行者情報(受注側の情報) | 会社名・住所・担当者名・電話番号・メールアドレスを記載する |
| 有効期限 | 見積もりが適用される期間を記載し、価格変動のリスクを回避する |
| 見積金額 | 合計金額を税込価格で記載し、誤解を防ぐ |
| 品名 | 商品やサービスの名称を具体的に記載する |
| 数量・単価 | ● 数量を明記する
● サービスの場合は「一式」と記載してもよい |
| 小計・消費税額・合計金額 | 合計金額が正しく計算されているか確認する |
| 通番(管理番号) | 自社での管理をスムーズにするための通し番号(任意) |
| 備考欄 | 納品条件や特記事項を記載し、トラブルを防ぐ |
有効期限・見積金額・発行者情報などは必須項目なので、漏れなく記載しましょう。
関連記事:建設工事の見積書の書き方を解説!概要や内訳・必要な項目を紹介
公的機関と契約を結ぶ際に注意したいこと
公的機関と契約を結ぶ場合、一般企業との契約とは異なるルールや注意点が存在します。
- 相見積もりではなく見積合わせと呼ばれる
- 公的機関との契約方式
- 見積合わせが行われる条件
- 公的機関との見積もりで法律違反になるケース
以下では、公的機関との契約におけるポイントを解説します。
相見積もりではなく見積合わせと呼ばれる
民間企業間の取引では、複数の業者から見積もりを取得する「相見積もり」が一般的です。
しかし、公的機関では「見積合わせ」と呼ばれます。
「見積合わせ」とは、複数の事業者から見積書を集めて契約を決定することです。
公的機関の場合は、随意契約を行う際に用いられることがあり、透明性の確保が求められます。
公的機関との契約方式
公的機関との契約には、大きく分けて3つの方式があります。
| 契約方式 | 特徴 |
| 一般競争契約 | 公告を行い、不特定多数の事業者が参加できる契約方式 |
| 指名競争契約 | 一定の基準を満たす事業者のみが参加できる契約方式 |
| 随意契約 | 公的機関が特定の事業者と直接契約を結ぶ方式 |
契約の種類に応じた適切な手続きを理解し、円滑な取引を進めることが大切です。
見積合わせが行われる条件
公的機関が見積合わせを行う際には、一定の条件が設けられています。
契約金額が、国や地方自治体が定める上限額以下であることが基本的な条件です。
少額随意契約の場合は、定められた範囲内であれば、複数の見積書から最適なものを選ぶ手法が取られます。
また、特定の業者との契約が適切と判断される場合も、見積合わせが行われます。
専門性の高い技術や、独自のサービスを提供する企業と契約する際に適用されることが多く、一般競争入札では適した業者が見つからない場合などに有効です。
さらに、公的契約では透明性の確保が求められます。特定の業者に偏らず、公平な競争が行われるように、複数の業者から見積書を取得するのが適切です。
契約の公正性を確保し、不正を防ぐための重要な仕組みとなっています。
公的機関との見積もりで法律違反になるケース
公的機関との契約においては、法律違反となるケースも存在します。事前に価格を調整し、談合を行うことは、競争を阻害する行為で厳しく禁止されています。
また、見積書を意図的に操作し、ほかの業者の見積額に合わせて不正に変更する行為も違法です。さらに、公的機関の職員が特定の業者を優遇する行為も、不正と判断される可能性があります。
公的機関との契約では、適正な手続きを遵守し、法律違反にならないように慎重に対応しましょう。
建設業向けの見積作成ソフトなら「Kensuke Neo」
「Kensuke Neo」は、建設業の現場で活躍する見積作成ソフトで、業務を大幅に効率化できます。Excelに慣れている方なら、直感的に操作できるのが特徴です。
また、アドバンのほかの業務ソフトと連携できるのもポイントです。見積作成だけでなく、請求書の発行や工事管理との統合が可能です。 データの一元管理により、業務の手間を減らし、ミスを防げます。
さらに、製品を使いこなせるように、操作に関する相談が回数無制限で受けられます。過去に、ほかの建設ソフトを導入したものの、操作が難しく活用できなかった企業におすすめです。
建設業に特化した見積作成ソフトをお探しの方は、ぜひ「Kensuke Neo」の導入を検討してみてください。
建築見積ソフト「Kensuke NEO」の導入事例

ここでは、建築見積ソフト「Kensuke NEO」を導入した企業の事例について見てみましょう。
株式会社山上組様の導入事例
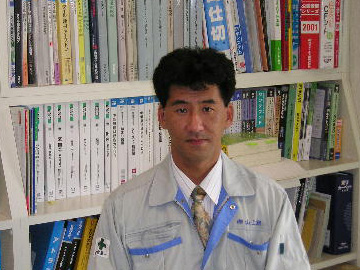
山上組様では、積算作業の効率化と属人化が課題でした。Kensuke NEOを導入した結果、誰でも短期間で習得可能な操作性と、柔軟なシステムの使いやすさに驚きました。
導入後は手作業に比べて5〜10倍の効率化を実現し、アフターサポートの充実も高く評価されています。
株式会社ナカシロ様の導入事例

ナカシロ様は、積算業務の手間を軽減するためにKensuke NEOを導入しました。2ヶ月間の試用期間中に、実物件を使用してソフトをテストし、操作方法をマスター。
建築部員の全員が操作できる体制を整えています。
石坂建設株式会社様の導入事例

石坂建設様では、従来の手作業による積算が業務に支障をきたしていました。Kensuke NEOの導入により、作業効率が大幅に向上し、見積の作成に十分な余裕が生まれました。
導入以来、効率的な積算が可能となり、今では欠かせないツールとなっています。
見積書を発行しなくても法律違反にならないが、トラブルを避けるために重要!
見積書の発行は法律上の義務ではありません。しかし、業界によっては必要になる場合があります。建設業では、建設業法により見積書の提出が義務付けられています。
また、PDFで発行した見積書の法的効力は紙と同等ですが、取引先の確認や改ざん防止策を行うことが大切です。本記事を参考に、見積書の適切な取り扱いを理解し、取引のスムーズな進行とトラブル防止に役立てましょう。
【アドバンが提供するサービス一覧】
- 建築見積ソフト「Kensuke Neo」
- 仕上積算ソフト「Neo仕上」
- 工事原価計算ソフト「Neo原価」
- RC躯体積算ソフト「松助くん」
- 作業日報管理ソフト「Neo日報」
- ワークフロー管理ソフト「ネオ ワーク」

株式会社アドバン代表取締役社長
「建設関連ソフトを通して世の中に貢献する」がモットーです。
創業から20年以上、重要な業務である積算や見積書作成などの効率化・高精度化に貢献したいとの思いで、建設業に特化したシステムの開発に取り組んできました。
すべてのソフトで無料で使用評価をいただくことが可能であり、ほとんどのお客様に十分納得をいただいたうえで、システムを導入していただいています。