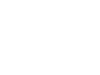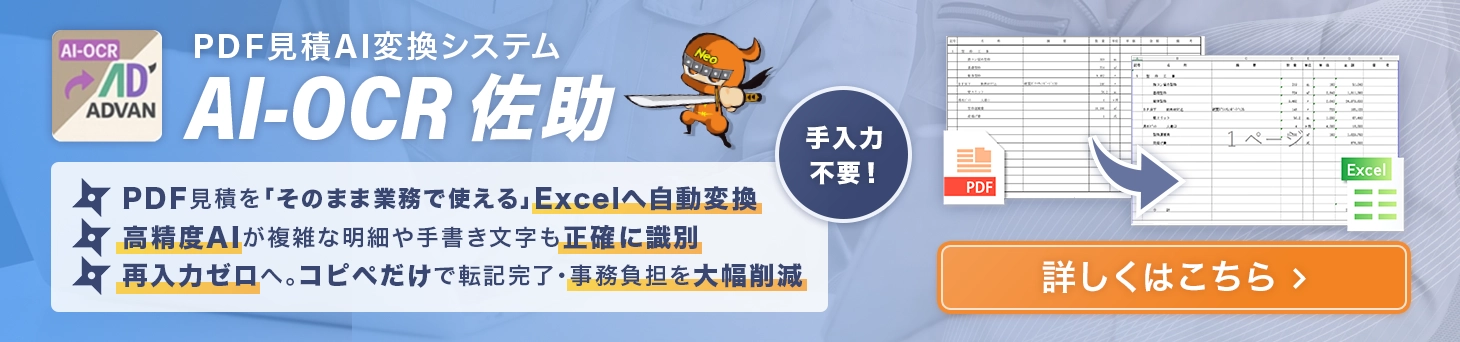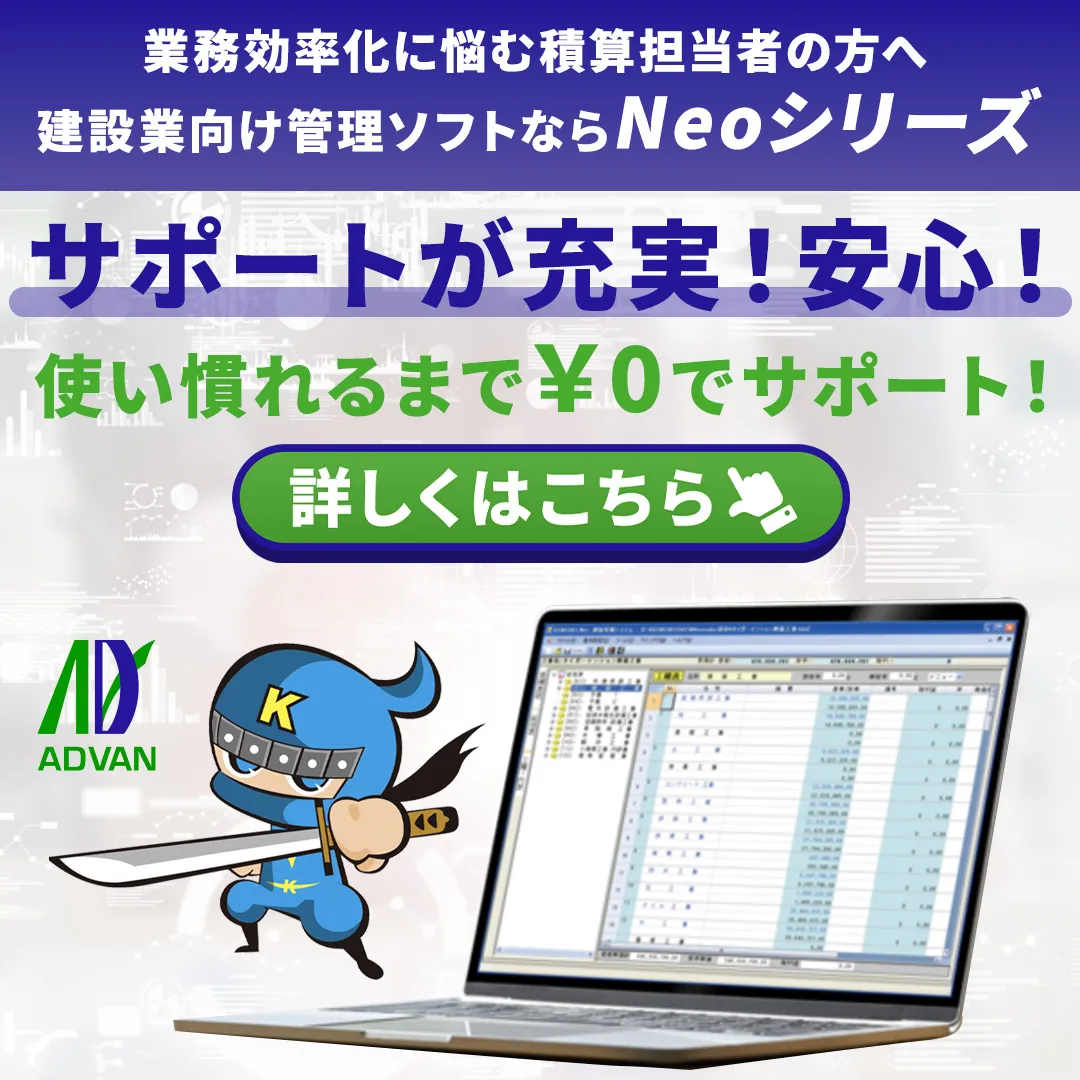Excelで原価管理を行う方法&おすすめの管理システム3選

建設業で原価管理の効率化をしたいと考えている方に向けて、Excelでの原価管理について解説する記事です。
原価管理で第一の選択肢になることが多いのがExcel。
しかし「Excelを使ってもイマイチ効率が良くない」「そもそも原価管理の方法がよくわからない」と思われている方もいらっしゃるものです。
そこで今回の記事では、Excelで効率的に原価管理を行う方法と、Excelで管理するメリット・デメリットをご紹介します。
おすすめの原価管理システムも掲載していますので、参考にしていただければ大幅に業務効率がアップするかもしれません。
原価管理とは

「原価管理」とは、業務を遂行するにあたって発生する原価を管理することです。
原価を管理することは、コストを最適化し、利益をさらに高めるために非常に重要なこと。
たとえば販売している商品・サービスが売れたとして、原価が高すぎれば利益は少なくなってしまいます。
またコストを削減するなど、商品・サービスの価格を適正に設定するためにも原価管理が必要となるでしょう。
原価管理はExcelで行う場合も、その他のシステムで実施する場合も、次の4つの要素を用いて進めていくのが基本です。
【原価管理のために必要な要素】
- 標準価格を設定すること
- 実際の原価を把握すること
- 差異を分析すること
- 改善案を実施すること
4つの要素を用いて管理することにより、原価を適切に調整して予算に対して適切な購買ができるようになります。
またいずれかの要素が予算よりも高くなってしまった場合、その他の要素を調整することも可能となるでしょう。
原価管理とは企業がサービス・商品を提供するにあたって、原価を適切に調整し、適切な利益を上げるために欠かせないことです。
Excel(エクセル)での原価管理方法
それではExcelで原価管理をする方法について見ていきましょう。
関数を活用する
Excelで原価管理をするなら、関数を活用して効率性を高めましょう。
関数を利用すれば、原価管理は比較的短時間で終えられます。
とくに次のような関数が役立つはずです。
【原価管理に役立つ関数】
- SUMPRODUCT:複数の範囲にある数字を合計する
- SUM:SUMPRODUCTよりも狭い範囲の数字を合計する
- AVERAGE:指定した範囲内の平均値を割り出す
- COUNT:指定した範囲内のセルの個数を数得る
- IF:指定した条件に沿った結果を導き出す
- VLOOKUP:指定した範囲内から検索結果を導き出して値を返す
ご紹介した関数を利用すれば、電卓を使っていたような計算も一瞬で結果を導き出せます。
特にSUM関数とIF関数は、原価管理においてさまざまなシーンで役立つでしょう。
中でも難易度の低い関数ばかりですので、Excelで原価計算をするならぜひご紹介した関数をマスターしてください。
テンプレートを作成する
Excelで原価管理を始める際に、ぜひ作っておきたいのがテンプレートです。
あらかじめテンプレートを作成しておくと、あとは数値を入力するだけで作業を進められるようになります。
毎回イチから原価管理表を作成しようとすると、どうしても手間がかかってしまうもの。
テンプレートを作成しておくことにより、原価管理を始めるための手間を削減できます。
Excelに搭載されているテンプレートをそのまま使っても良いですが、より自社に適した形にするなら、最初に作成して保存しておく方法がおすすめです。
テンプレートを作成するときのポイントは、必要な項目を入力しておくことと、セルを設定しておくことです。
原価管理に必要な項目を洗い出したうえで入力し、数値を入力しただけで計算が完了するようにしておくと便利でしょう。
テンプレートを作成すると、Excelでの原価計算が格段に容易になります。
関連記事:【建設業向け】Excel帳票の作り方とは?メリット・デメリットも
Excel(エクセル)で原価管理するメリット
Excelで原価管理をするためのポイントについて触れてきました。
しかしその他のソフトウェアでも原価管理はできます。
それではExcelで原価管理をすることにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
代表的な4つのメリットについてご紹介します。
メリット①コストを抑えられる
Excelを使うと、原価管理のためのコストを抑えられるようになります。
専用のシステムも販売されていますが、やはり導入するとなると初期費用やランニングコストがかかるものです。
しかしExcelであれば多くの企業ですでに導入されており、追加費用をかけなくても原価管理ができるようになります。
もしExcelを新たに導入するとなっても、専用のシステムよりも安価となるでしょう。
原価管理のためのコストを押さえられることは、Excelを利用する大きなメリットとなります。
メリット②社員教育の時間を削減できる
社員教育の時間を削減できることもメリットのひとつです。
特別な教育をしなくても、Excelを使える方は多いもの。
もし専用システムを導入するとすれば、操作方法についての教育をしなければなりません。
しかしExcelであれば使い慣れている方が多く、特別な教育は必要なくなるでしょう。
社員の教育にも工数や人件費がかかります。
教育が不要となることでコスト削減につながりますし、無駄な工数をかけなくて済むようになるはずです。
メリット③テンプレートで業務を効率化できる
Excelで原価管理をすると、テンプレートで業務を効率化できるようになります。
テンプレートを使う方法がおすすめであることは先に解説しました。
用途に適したテンプレートを利用することで、業務効率化が推進されます。
自社でオリジナルのテンプレートを作成しても良いですが、Excelでは既存のテンプレートが多数配布されています。
普及率が高いアプリケーションであるため、原価管理のためのテンプレートも見つかるでしょう。
業務効率化のためにテンプレートを利用できることは、原価管理でExcelを利用する魅力とも言えます。
メリット④自由にカスタマイズできる
自社にあわせて自由にカスタマイズできることもメリットでしょう。
Excelは原価管理専用のシステムよりも自由度が高く、自社に適した形へとカスタマイズができます。
マクロやVBAを利用すれば、より高度なカスタムも可能です。
専用システムを導入しても、自社に適するかどうかはわかりません。
むしろExcelをカスタマイズしたほうが、自社の原価管理を行いやすくなることもあるでしょう。
Excel(エクセル)で原価管理するデメリット

Excelで原価管理をすることは、メリットばかりではありません。
デメリットもあるので、これからExcelを用いた原価管理を始めようかと思われているなら、デメリットも知っておきましょう。
デメリット①人的ミスが発生しやすい
Excelでの原価管理の最大のデメリットとも言えることが、人為的ミスが発生しやすいことです。
人が手で数値を入力しなければならないため、どうしてもミスが起こり得ます。
目視でチェックをしていたとしても、見逃しをゼロにすることは難しいでしょう。
ミスに気づかなければ、原価を正しく管理できているとは言えません。
人が入力しなければならないからこそ、人為的ミスが起こりやすくなることは大きなデメリットです。
デメリット②業務が属人的しやすい
業務が属人化しやすいこともデメリットのひとつであると言えます。
なぜなら関数やマクロを使用するには、ある程度の知識が必要となるためです。
そうなると「Excelで原価管理を行う担当者」が中心となり、管理を行うことになります。
Excelの基本的な使い方は多くの方が知っているでしょうが、複雑な関数やマクロとなると話は別。
プログラミングに近い知識が必要となり、Excelに詳しくない方には難しいことも考えられます。
そのため業務が属人的になりやすく、担当者がいなかったり辞めてしまったりすると原価管理ができないことにもなりかねません。
デメリット③複数人で作業できない
Excelで原価管理をするデメリットとして、複数人での作業ができないこともあげられます。
Excelでは1人しかファイルの編集をできない仕様であるためです。
またファイルの共有が難しいことも理由のひとつであると言えるでしょう。
ファイルの共有に関してはクラウドやサーバーに保存をするのであれば問題ありません。
しかし設備が整っていなければ、メールで送信するなどの手間がかかります。
またクラウドやサーバーに保存していたとしても、複数人での同時編集はできないことに注意してください。
誰かが編集し終わるのを待たなければならなくなり、原価管理によって業務効率が下がることも考えられます。
Excelは原価管理に適したアプリケーションですが、複数人で作業をしなければならない場合、不便さを感じるかもしれません。
デメリット④ファイルが管理しにくい
ファイル管理がしにくいこともデメリットだと感じられるでしょう。
Excelではファイルの一元管理ができず、更新作業に時間がかかることがあります。
一元管理するにはリアルタイムでの更新が必要となりますが、データを共有しにくいのがExcel管理のデメリット。
たとえばローカルディスクにファイルを保存すると、原価を入力したいその他の方にメールなどでファイルを送付しなければなりません。
すると起こる問題が、最新のデータがわからなくなることです。
送信・受信・編集を繰り返しているうちに、どのファイルが最新のものかわからなくなってしまう恐れがあります。
古いファイルで上書き保存をしてしまうと、原価管理に抜けや漏れが生じてしまうでしょう。
ファイル管理がしにくいことは、Excelでの原価管理の大きなデメリットのひとつです。
デメリット⑤セキュリティ対策が万全でない
最後に、セキュリティ対策が万全ではないことについてです。
ExcelファイルはUSBなどに保存して、簡単に外部に持ち出せます。
メールに添付して送信することも容易です。
そのためセキュリティ対策が万全であるとは言えません。
専用のシステムであればデータの持ち出しは難しく、セキュリティリスクを最小限に抑えられます。
Excelで原価管理をすることは、セキュリティリスクと隣り合わせであることを念頭に置きましょう。
建設業向けおすすめの原価管理システム
Excelでの原価管理にはメリットもありますが、やはりデメリットもあります。
より安全で、より使いやすい環境を構築したいと思われるなら、やはり専用システムの導入がおすすめです。
そこで建設業向けのおすすめ原価管理システムを3つご紹介します。
数あるシステムの中から厳選しましたので、原価管理の体制を改善したいと思われているならぜひ参考にしてください。
関連記事:建設業向けの原価管理ソフトとは?メリットや選び方を解説
①Neo原価
「Neo原価」は1,000社以上で導入されており、操作が簡単なことが魅力の原価管理ソフトです。
Excelの感覚で原価管理ができるので、Excelとシステム導入のどちらかで迷われている方にもおすすめします。
インボイス制度にも対応していますし、IT導入補助金も利用可能です。
Excelでの原価管理はコストを抑えられることがメリットでしたが、IT導入補助金を利用すれば、Neo原価の導入費用も大幅に抑えられるでしょう。
データを入力すれば、原価だけでなく注文稟議書や注文書、支払査定、支払まで一貫した管理が可能となります。
利用すれば損益を把握しやすくなるため、企業の利益率アップにも貢献するはずです。
操作性が簡単でExcelのように扱える原価管理ソフトをお求めの方には最適ではないでしょうか。
関連記事:建設業向けの原価管理ソフトおすすめ16選&選び方のポイント
②どっと原価シリーズ
建設業向けの原価管理に、標準化・効率化をもたらすのが「どっと原価シリーズ」です。
集計によると、導入によって集計の作業時間が約80%、請求などに関する業務ステップ数が約70%されました[1]。
カスタマイズ可能であり、Excelでの原価管理よりも、さらに自社に適した形で運用できるでしょう。
機能が随時更新されているので、導入後にさらに使い勝手が良くなることもあります。
建設業の原価管理をもっとスマートにしたいとのニーズに最適です。
③楽楽販売
「楽楽販売」は「脱Excelの原価管理」によって、転記ミスを削減し、収支をリアルタイムで把握できるようにするシステムです。
原価計算や請求、計上処理を自動化させられるため、人為的ミスを削減できるでしょう。
売上と原価を紐づける機能も搭載されており、収支確認も実施しやすい仕様です。
原価管理はもちろん、見積管理や受注管理、請求管理、発注管理も行えます。
MA・SFAツールや会計ソフトとの連携も可能であり、社内のシステムをまとめて自動化させたいときに便利です。
Excelでの原価管理にはメリットもデメリットも
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、Excelでの原価管理についてご理解いただけたと思います。
手軽に低コストで導入できるものの、人為的ミスがおこりやすい、データ共有が難しいなどのデメリットもありました。
その点、「Neo原価」はExcel感覚で使え、Excel以上の原価管理効率化をご提供するシステムです。
もしどのような形で原価管理をすべきか悩まれているなら、ぜひNeo原価の導入をご検討ください。
[1]
参照:どっと原価:建設業向け原価管理システムならどっと原価シリーズ|建設ドットウェブ

株式会社アドバン代表取締役社長
「建設関連ソフトを通して世の中に貢献する」がモットーです。
創業から20年以上、重要な業務である積算や見積書作成などの効率化・高精度化に貢献したいとの思いで、建設業に特化したシステムの開発に取り組んできました。
すべてのソフトで無料で使用評価をいただくことが可能であり、ほとんどのお客様に十分納得をいただいたうえで、システムを導入していただいています。