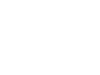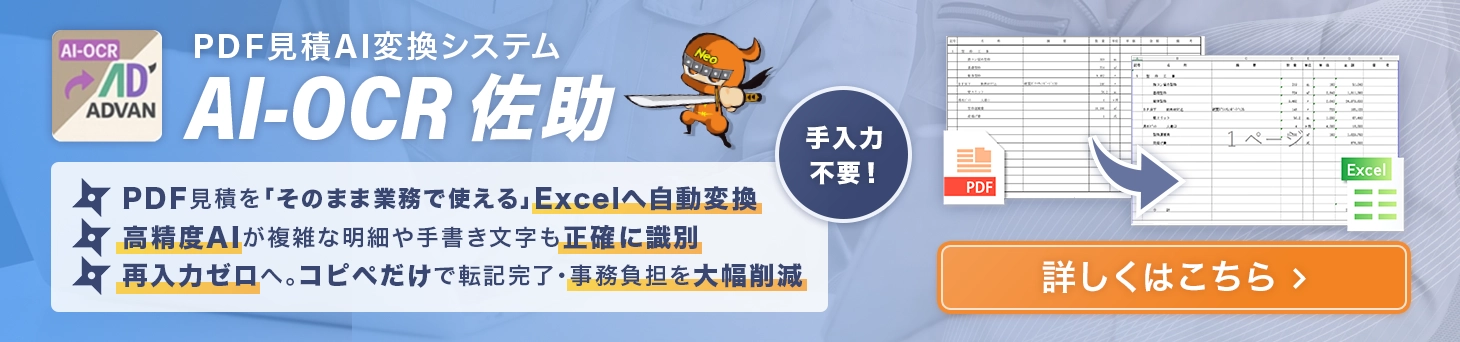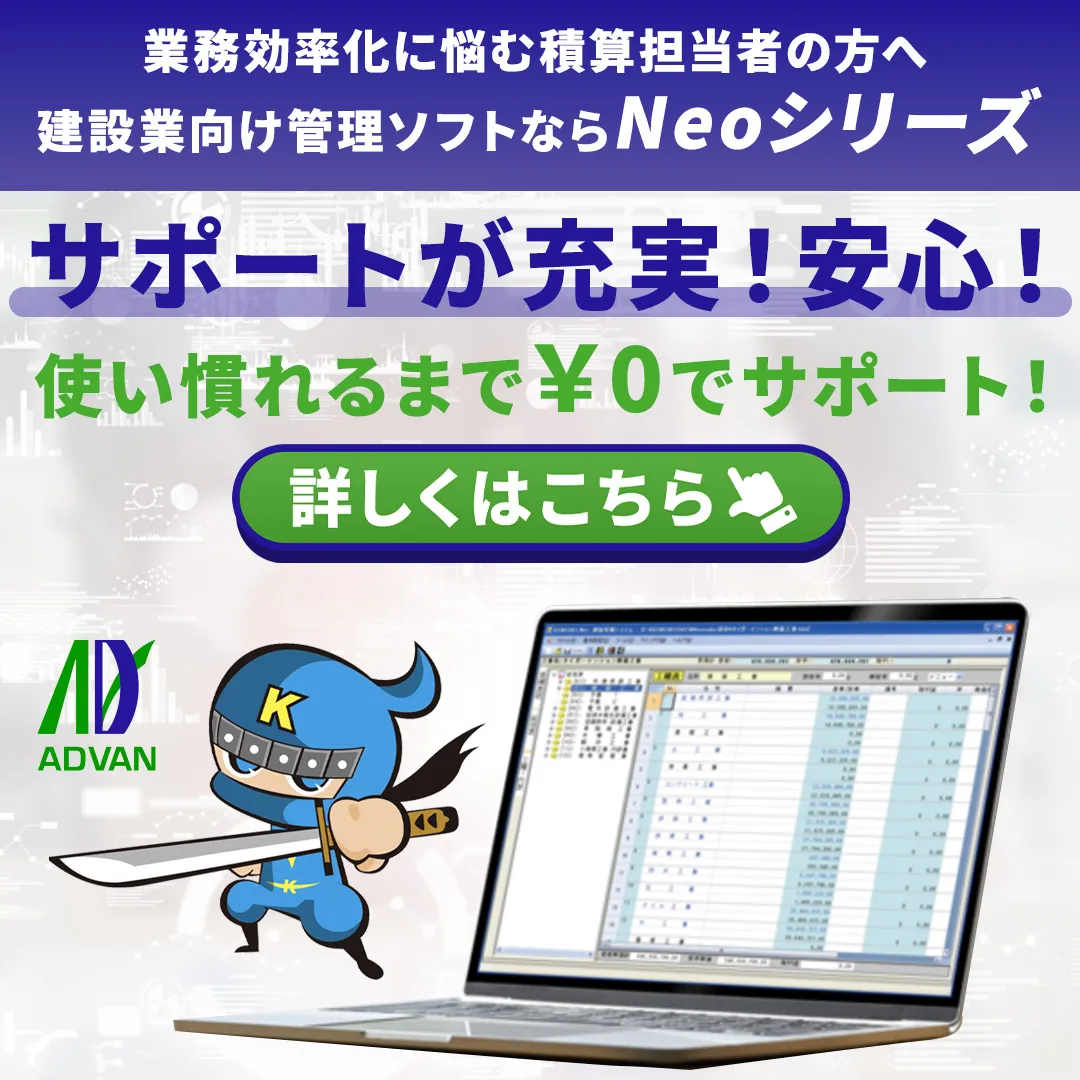工事原価とは?原価率の計算方法と管理方法の効率化について

工事に関する事務作業を効率化したい方に向けて、工事原価の基本をわかりやすく解説します。
工事原価は建設業において重要な概念です。 しかし「工事原価を計上するやり方がわからない」「もっと効率的に計上したい」とお悩みの方も少なくありません。
本記事では、工事原価に関する基礎知識や種類、計算方法を解説します。さらに効率的に管理する方法も紹介し、実務に役立つ知識を提供します。 工事原価をより効率的に管理するための方法にも触れていますので、参考にしていただければこれまでよりも工事原価管理がスムーズになるはずです。
建設業における工事原価とは

「工事原価」とは、建設業特有の会計科目で、工事に必要となった費用をまとめたものを指します。
ただし、単独の勘定科目名として「工事原価」は存在しません。 費用は通常、材料費・労務費・外注費・経費に区分されます。 また、収益性を測る指標として「粗利益率」や「工事原価率」が用いられます。
完成工事原価
まず「完成工事原価」とは、売上原価を指し、建設に必要な材料費や労務費、外注費、経費などを含みます。
工事は長期にわたる作業となることも少なくなく、完成工事原価は工事の完了に対応して売上原価として計上します。 収支を把握するために欠かせない要素であり、完成工事総利益を算出する際にも用いられます。 以上のとおり、工事に直接要した費用を集計するのが完成工事原価です。
未完成工事支出金
「未完成工事支出金」とは、未完了の工事に対して必要となった費用のことを指します。
建設業ではひとつの工事を完了させるための期間が長く、かかった費用を当年度に計上できないこともあるでしょう。 たとえば、工事が未完成のまま年度を終えると、費用を次年度に繰り越さなければなりません。 そこで未完成工事支出金として、次年度に繰り越す処理が行われます。
そのため、短期間で完了する工事であれば必要のない科目です。 長期で年度をまたぐ場合は、当該費用を未完成工事支出金として処理します。
粗利益率
工事の売上高の中の、粗利益の割合を示すのが「粗利益率」です。 計算式は次のとおりです。
粗利益率(%)=粗利益÷売上高×100
ちなみに、粗利益を算出する計算式は次のようになります。
売上高-工事原価
売上高と工事原価のバランスを把握するために有用な指標です。
適正水準は企業規模や案件特性で異なるため、自社の原価構造や市場環境に応じて目標値を定めることが重要です。
工事原価率
「工事原価率」とは、売上高に占める原価の割合を示す指標です。 売上に対してどれだけの費用が発生したかを表します。
粗利益率が売上高に対する粗利益の割合を示すのに対し、工事原価率は売上高に対する費用の割合を示します。 工事にかかった費用の割合を算出するためのものが工事原価率です。
工事原価の4つの要素
工事原価は、材料費・労務費・外注費・経費の4つの要素で構成されます。 それぞれの内容を以下で解説します。
材料費
「材料費」とは、工事に必要な木材や鉄材、セメント、ガラスなどの材料を調達するために要した費用を指します。
材料費はさらに次の2種類にわけられます。
| 直接材料費 | ひとつの工事で用いられる材料のこと | 木材やガラスなど |
| 間接材料費 | 複数の工事で用いられる材料のこと | 塗料や施工のための工具類など |
特定の工事にのみ使用する材料は直接材料費です。 一方、複数の工事で共通して使用する材料は間接材料費と呼ばれ、工事ごとに按分して計上します。
以上2種類の費用をまとめたものが「材料費」です。
労務費
工事に従事する労働者に支払う費用が「労務費」です。 工事を遂行するには人員の確保が不可欠であり、雇用には賃金だけでなく福利厚生費や各種手当など多様な費用が発生します。 人を雇うためにかかった費用をすべてまとめて労務費とします。
外注費
「外注費」は、作業の一部を外注したときに発生する費用のことです。 自社で全てを実施する場合は発生しませんが、建設業では外注するケースが多く、工事原価に占める割合も大きいため外注費の科目が設けられています。
たとえば、材料の一部を他社に外注することもあるでしょう。 建設作業自体を外注することもあるかもしれません。 工事に伴い他社へ業務を委託した場合に発生するのが外注費です。
経費
「経費」とは、材料費・労務費・外注費のいずれにも該当しない費用を指します。 設計や動力源にかかる費用、建設機械の減価償却費、メンテナンス費用などは経費として計上してください。 工事を行うにはさまざまな業務があり、減価償却が必要な機械も投入されるでしょう。 分類が難しい費用についても、経費として処理するのが一般的です。 材料費・労務費・外注費のいずれにも該当しない費用は、経費として処理するのが慣例です。
工事原価率の計算方法

工事原価率は次のような計算式で求めてください。
工事原価率(%)=工事原価÷売上高×100
ひとつ前の項目で解説しましたが、工事原価に該当する費用は次の4つです。
| 材料費 | 工事のために必要となった材料の購入費用 |
| 労務費 | 工事を施工した人に対して支払う費用 |
| 外注費 | 工事作業の一部を外注したときに発生した費用 |
| 経費 | 上記3つのいずれにも該当しない費用 |
売上高とは、工事によって発生した収入です。 すべての工事原価を合計し収入で割ったうえで100を掛けると、工事原価率を算出できます。
工事原価管理の重要性
工事原価管理は建設業において極めて重要であり、不適切な管理は経営危機を招く恐れがあります。 工事原価管理が重要とされる理由を以下に解説します。
①利益確保のために役立つ
まず、工事原価管理は利益確保のために役立ちます。 工事にかかった費用を適切に把握できるようになるため、ひとつの工事ごとの利益を確保するために欠かせません。 売上高だけを見ていても、実際の収益は把握できません。 工事原価管理を徹底することによって、企業の実際の利益を確保しやすくなります。
②無駄な費用を削減できる
無駄な費用を削減するためにも工事原価管理が必要となります。 工事原価率を管理することによって、工事にどのくらいの費用がかかっていたのかを把握できるようになるためです。
利益は「売上高-かかった費用」によって算出されます。 売上高が多くても、比例して費用も高額になっては十分な収益は得られないでしょう。 特に、建設業では人件費や材料費が高騰しており、工事原価管理の見直しが求められています。 工事原価には人件費も含まれているため、業務効率化を図り、人件費の削減を目指すことも重要です。
工事原価を管理すれば無駄な費用が生じている部分を見つけやすくなり、費用削減および収益アップにつながります。
③損益分岐点を判断しやすくなる
損益分岐点を判断しやすくなることも、工事原価管理が必要とされる理由のひとつです。
損益分岐点とは、企業の赤字と黒字を決めるラインとも言えます。 収入と支出のバランスを確認することにより、赤字となっているか黒字となっているかを判断しやすくなるでしょう。
とくに建設業は、ひとつの業務にかかる期間が長くなる傾向があり、収支の管理を徹底しなければ損益分岐点がわかりにくくなってしまうものです。 企業を健全に運営するためには、損益分岐点を常に意識することが重要です。 工事原価管理を行うことで、自社の経営状態をより明確に判断できます。
④経営の健全さを示しやすくなる
投資家や取引先などに対して、経営の健全さを示しやすくするためにも工事原価管理が役立ちます。 完成工事原価報告書を適正な形で提出できれば、投資家や取引先からの評価が上がることもあるでしょう。 透明性の高い企業であると判断されるため、経営を進めるうえで大きなメリットがあります。
これは企業の信頼性を高めることにも直結します。 工事原価管理を適切に行うことにより経営の健全さを周囲に示すことができれば、自ずと企業の信頼性も高まっていきます。
関連記事:建設業の工事原価管理とは?難しいといわれる理由も解説
工事原価を効率良く管理する方法
それでは最後に、工事原価を効率よく管理する方法をご紹介します。
工事原価を効率よく管理するには、専用のシステムを導入するのが最善の方法です。 Excelを活用する方法もありますが、Excelだけではどうしても不便さを感じてしまうことがあるでしょう。 たとえば次のようなことです。
【不便さを感じるポイント】
- 手入力による人為的ミスの多さ
- セキュリティリスクの高さ
- ファイルを共有しにくい
- 専門的な操作に関して業務属人化が起こりやすい
- 複数人での作業がしにくい
Excelは手軽に導入できる点が魅力ですが、業務効率化を徹底するには限界があります。 そのため本当の業務効率化を目指すのであれば「Neo原価」をおすすめいたします。 Neo原価は、Excelに近い操作性を持ちながら、見積データから支払までを一貫して管理できます。 さらに業務フローに合わせたカスタマイズも可能で、自社に最適な工事原価管理システムを構築できます。 人為的ミスを削減でき損益状況を迅速に把握できるため、経営判断にも役立てていただけるでしょう。
無料トライアルも用意されており、自社に適したシステムかどうかを判断しやすくなっています。 工事原価管理の効率性を重視されるなら、Neo原価の導入をご検討ください。
関連記事:Excelで原価管理を行う方法&おすすめの管理システム3選
工事原価は収支を把握するための重要なカギ
いかがでしたでしょうか? この記事を読んでいただくことで、原価管理についての知識を深めていただけたと思います。 工事原価は収支を把握するためのカギであり、適切に管理すると経営判断も容易となるでしょう。
「Neo原価」はExcelのような操作感でありながら、より高度な機能を備えています。 工事原価管理を徹底したい企業は、無料トライアルを利用して導入を検討できます。

株式会社アドバン代表取締役社長
「建設関連ソフトを通して世の中に貢献する」がモットーです。
創業から20年以上、重要な業務である積算や見積書作成などの効率化・高精度化に貢献したいとの思いで、建設業に特化したシステムの開発に取り組んできました。
すべてのソフトで無料で使用評価をいただくことが可能であり、ほとんどのお客様に十分納得をいただいたうえで、システムを導入していただいています。