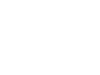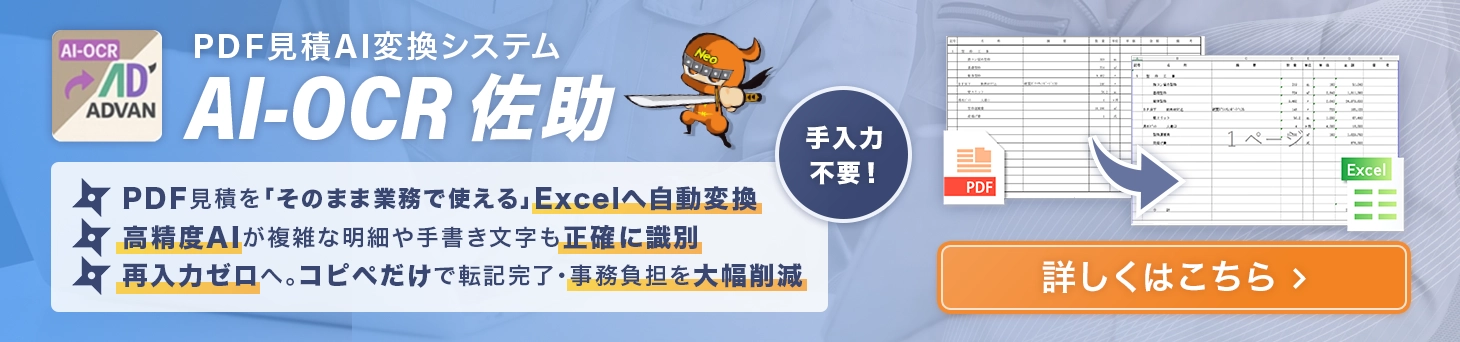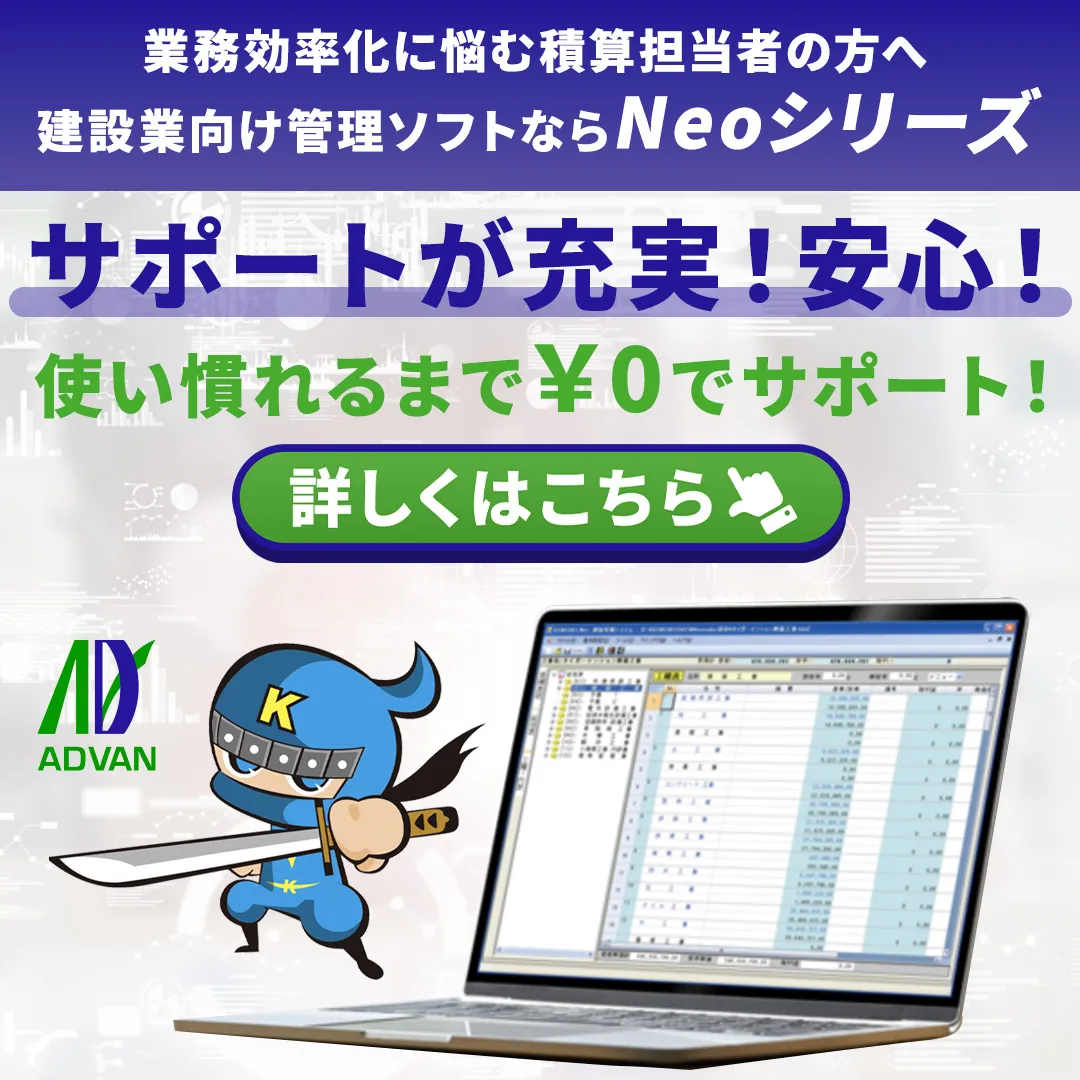工期短縮を効率的に行う方法とは?メリットや注意点を解説

建設プロジェクトにおいて、工期短縮は利益確保や顧客満足度の向上に直結する重要な取り組みとされています。
本記事では、工期短縮の目的やメリット、実施方法、導入時の注意点について解説します。
現場で無理なく効率化を進めるためのポイントを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
工期短縮とは?
工期短縮とは、建設工事にかかる期間を意図的に短くする取り組みを指します。
工期とは着工から竣工までの工程を指す建設業特有の用語であり、これを適切に管理・調整することが工期短縮の目的となります。
近年では、働き方改革や人材不足といった業界全体の課題を背景に、限られたリソースの中で成果を最大化する必要性が高まっており、多くの現場で工期短縮の工夫が求められています。
工程の最適化やITツールの導入など、さまざまな方法によって実現できます。
工期短縮を行うべき理由
工期短縮を進めるべき背景には、労働環境の変化や法改正があります。
建設業界では、2024年4月から時間外労働の上限規制が本格的に適用されるようになり、長時間労働が許されない環境が整いつつあります。
こうした状況下では、従来のやり方のままでは現場が回らなくなる恐れもあるため、作業の効率化や工程の見直しによる工期短縮は、もはや不可避の課題となっています。
加えて、工期を短くすることで人件費や資材使用の最適化にもつながり、経営面でのコスト圧縮にも効果が期待できます。
※参照元:厚生労働省(働き方改革関連法のあらまし)
工期短縮を行うメリット
工期短縮は単なる作業スピードの向上にとどまらず、組織全体の働き方を見直す契機となり、持続的な利益体質への転換を促します。
建設現場における工程を見直し、効率化を図ることで得られるメリットは多方面に及びます。
以下では、コスト・業務・企業戦略の3つの観点から、工期短縮による代表的なメリットを解説します。
コスト削減につながる
工期が短くなることで、まず現場で発生する直接的なコストを大きく圧縮できます。
例えば、人件費や作業員の宿泊費、仮設資材のレンタル料、重機や車両の稼働費などは日数に比例して増加するため、工事期間を短縮するだけで支出が減る仕組みです。
また、現場事務所や材料置き場の借用期間も短縮されることで、現場の固定費削減にもつながります。
さらに、工期を短くしようと工程を見直すことで、設計者と施工者の連携も強化され、設計変更や工程の手戻りといった余分なコストの発生も回避しやすくなります。
生産性が向上する
工期短縮を実現するには、工程全体のムダや非効率な作業手順を洗い出し、業務の合理化を図る必要があります。
その過程で業務フローが整理され、業者間の連携や作業の段取りが明確になるため、その結果、現場全体の生産性が向上します。
また、短い期間で集中して作業する体制が整えば、作業員のモチベーションや集中力も高まり、質を維持しながら安定した進捗管理が可能になります。
効率的な現場運営は結果的に働きやすい環境づくりにも貢献し、従業員満足度の向上や人材確保にも良い影響をもたらします。
競争力が向上する
短い期間で工事を安全かつ高品質に完了させた実績は、企業としての信頼性を高める大きな要素です。
発注者にとって「納期を守れる企業」という評価は価格以上に重視されるケースも多く、入札や提案競争での選定理由になり得ます。
また、効率よく複数案件を回せる体制が整えば、同時並行での受注が可能になり売上機会の増加にも直結します。
こうした実績の積み重ねは、自社のブランド力向上や長期的な経営基盤の強化にも貢献します。
協力体制を強化できる
工期短縮を現場全体で達成するには、監督者・協力業者・職人・設計担当など、すべての関係者が一丸となって綿密な連携を取らなければいけません。
スケジュールや作業内容の共有が日常的に行われると、組織内のコミュニケーションが活発になり、トラブルの早期発見や業務の柔軟な調整も可能になります。
また、厳しい工程を共に乗り越えた関係性は信頼を生み出し、次回以降のプロジェクトでも強固な協力関係が築かれていきます。
このような体制の構築は、長期的に安定した現場運営に欠かせない要素の一つです。
工期短縮を行う方法
工期短縮を実現するには、現場作業のスピードを上げるだけでなく、構造設計や施工方法、現場環境、業務フローなどあらゆる側面の見直しが求められます。
無理な突貫作業ではなく、効率的かつ安全に工事を進める工夫が、持続可能な工期短縮の実現に欠かせません。
ここでは、現場で役立つ4つの具体的なアプローチについて見ていきましょう。
構法・工法を見直す
工期短縮を図る際、まず見直したいのが構法と工法です。
構法とは建物の構造や使用資材の組み立て方を意味し、工法は施工の手順や技術を指します。
例として、ユニット化された部材の採用やプレキャストコンクリートの導入は、現場での作業工程を削減し大幅な時短を可能にします。
また、ロボット施工や省力化工法など、現場の人員負荷を軽減しながら施工スピードを高める方法もおすすめです。
天候による影響を受けにくい乾式工法やプレファブ化の活用は、現場の不確実性を減らす手段として注目されています。
構法や工法の工夫は、作業効率や安全性の向上にも寄与する重要な施策といえます。
工程の適切な管理を行う
工期を効率的に短縮するには、作業を単純に急がせるのではなく、工程の組み方を根本から見直さなければいけません。
作業の中には、多少遅れても影響の少ないものと、わずかな遅延でも全体を止めてしまうクリティカルな工程があります。
これらの違いを見極め、優先順位を正しく設定し、並行可能な作業は並行して進めることで大幅な時間短縮が可能になります。
ネットワーク工程表などを用いて全体の工程を可視化し、依存関係や作業間のタイミングを把握する必要があるでしょう。
最近では、工程管理システムやクラウド型のスケジューリングツールを導入することで、リアルタイムで進捗を共有し遅れへの即時対応も可能になっています。
こうした管理体制の整備は、計画的な工期短縮を進める上での第一歩となります。
工事における制約条件を緩和する
工事現場には、安全・品質を保つための多くの制約条件が存在しますが、すべてが実務に適した内容とは限りません。
発注者側が課す仕様の中には、実際の作業にとって非効率な指示や過剰なルールが含まれていることもあります。
こうした制約が現場の足かせになっている場合、その背景や意図を丁寧に確認し、不合理な項目について緩和できるか提案してみるのも良いでしょう。
現場と発注者の信頼関係があれば、制約の見直しが可能になり、工期短縮にも直結します。
ただし、制約を緩和する際は、安全性や法令遵守が損なわれないよう注意してください。
無理のない範囲で作業の自由度を高めると、無駄な待機や段取り替えを減らし、スムーズに工程が進行するはずです。
ITツールを活用する
近年はITの力を借りて工期短縮を実現する現場が増えています。
図面や工事写真、工程表、発注書類などをクラウド上で一元管理することで、関係者間の情報共有がスムーズになり、意思決定や確認作業にかかる時間を大幅に削減できます。
また、チャットツールやスマホ対応の現場アプリを活用すれば、離れた現場間でもリアルタイムに状況報告や調整が可能です。
さらに、工程管理システムを導入すれば、遅れの早期発見や作業の再調整がしやすく、全体の最適化に役立つでしょう。
ITツールは作業速度を直接向上させるわけではありませんが、連絡のズレや確認ミスといった「見えないロス」を排除する上で非常に有効な手段です。
コストや操作性を十分に検討し、導入を進めましょう。
工期短縮を行う際の注意点
工期短縮は建設プロジェクト全体の効率を高め、利益向上につながる取り組みですが、やり方を誤れば思わぬトラブルや逆効果を招いてしまいます。
ここでは、工期短縮を安全かつ効果的に進めるために、前もって理解しておきたい5つの注意点を詳しく解説します。
無理のない範囲で行う
工期を縮める際は、あくまで「現実的に達成可能な範囲」で調整することが大前提です。
人員や資機材の手配、天候条件など、外的要因も加味しながら無理のないスケジュールを組まなければ、現場は混乱し、むしろ遅延や品質低下を招いてしまいます。
また、過度に圧縮された工期は、現場管理者や作業員に過剰なプレッシャーを与え、判断ミスや手戻りの原因にもなり得ます。
工程表を作成するときは、あらかじめ余裕時間(バッファ)を含め突発的なトラブルにも対応できる柔軟な設計が求められるでしょう。
労働環境が悪化してしまう場合がある
工期を短縮するために長時間労働や休日出勤を増やすという方法は、一時的には効果が出るかもしれませんが、中長期的に見ると労働環境の悪化を引き起こします。
特に現場作業では、疲労が蓄積すると事故や怪我のリスクが高まるだけでなく、作業精度の低下にも直結するでしょう。
結果的に職人の離職率が上昇し、人材不足という新たな課題が発生しかねません。
持続的な生産性向上を目指すならば、働き方改革の流れに逆行するようなスケジュール設計は避け、作業員の健康と士気を重視した現場づくりを意識する必要があります。
【関連記事】建設業はなぜ人手不足が進むのか? 原因と解決策をわかりやすく解説
安全管理と品質管理のバランスを取る
スピードを重視するあまり、安全管理や品質管理がおろそかになってしまうと、工期短縮の成果が帳消しになってしまいます。
安全確認を省略して発生した事故や、施工ミスによる補修工事が発生すれば、追加の費用と工期が必要になり本末転倒です。
工期短縮を進めるなら、工程のどこに重点を置くべきかをあらかじめ明確にし、検査や品質確認といった工程は決して省かず、必要な管理体制を維持しましょう。
効率化と安全・品質は相反するものではなく、計画的に調整すれば共存できるはずです。
工期短縮で原価削減ができるとは限らない
工期短縮=コスト削減と単純に捉えるのは危険です。
現場の作業員を増員すれば人件費が上がり、外注に頼れば調整費や管理費が発生します。
さらに、短期間で使用するために資材を緊急調達すれば、単価が割高になることもあります。
効率化を図るために新たな設備やシステムを導入する場合も、初期投資とのバランスを見誤ると、かえって原価が膨らむことになるでしょう。
工期短縮を進めるときは原価管理との連動を前提に、実際にどの程度の削減効果が見込めるのか数値で把握しておくと良いです。
短すぎる工期は避ける
2020年の「改正建設業法」によって、「著しく短い工期の禁止」が明文化されました。
この背景には、過度な短納期が現場に無理強いさせるばかりか、建設業界全体の人材流出や品質問題を助長してきたという実態があります。
発注者からの要望に安易に応じてしまい、現実離れしたスケジュールを引き受けると、後々トラブルに発展しかねません。
法令やガイドラインに基づいた適正な工期を提示し、その範囲内で最大限効率を高める努力を重ねることが、信頼される施工者としての姿勢にもつながります。
過度な期待に応えるのではなく、実現可能な工程を誠実に提案することが、結果的に事業の持続性を守るカギとなります。
※参照元:国土交通省(適正な工期の確保に向けた取組について)
効率的な工期短縮は、建設現場の競争力と持続性を高める
工期短縮は現場の効率化やコスト削減、生産性の向上に直結する重要な戦略です。
ただし、労働環境や品質、安全への配慮を怠れば逆効果になりかねません。
構法・工法の見直しやIT活用など、現場の特性に応じた対策を講じ、無理のない範囲で計画的に進めることが、建設業における持続的成長と信頼獲得につながります。

株式会社アドバン代表取締役社長
「建設関連ソフトを通して世の中に貢献する」がモットーです。
創業から20年以上、重要な業務である積算や見積書作成などの効率化・高精度化に貢献したいとの思いで、建設業に特化したシステムの開発に取り組んできました。
すべてのソフトで無料で使用評価をいただくことが可能であり、ほとんどのお客様に十分納得をいただいたうえで、システムを導入していただいています。