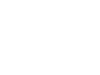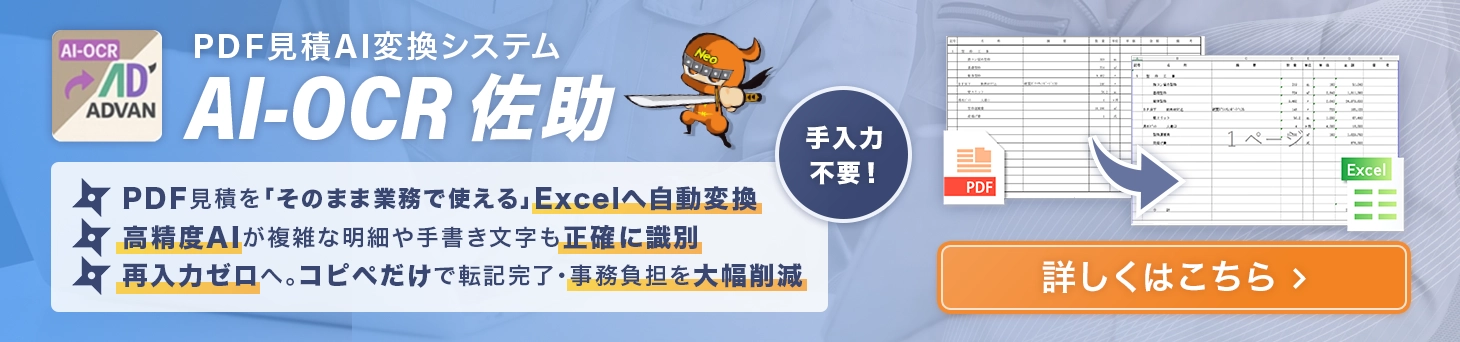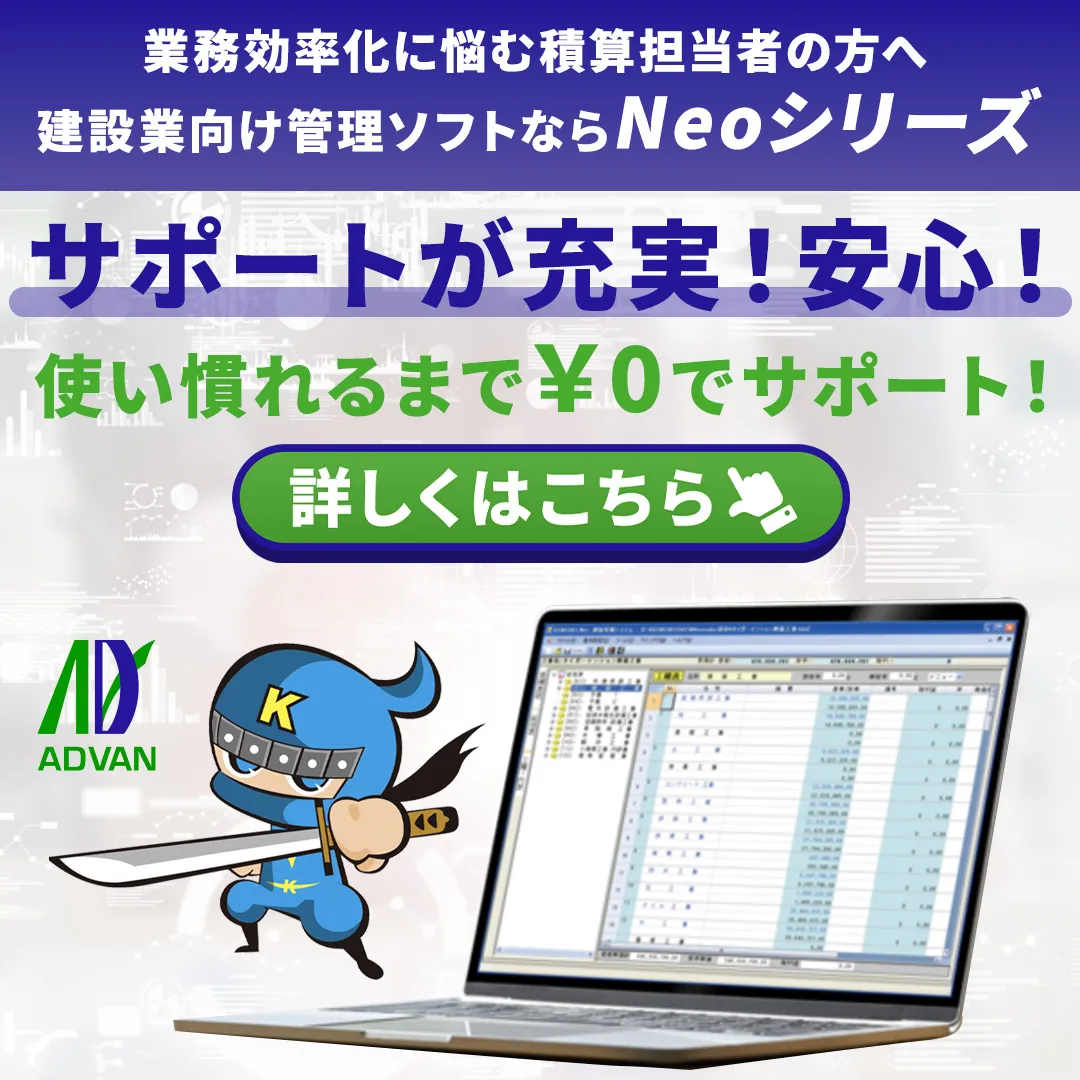建設業における帳票の特徴とは?保存期間や適切な保管方法も解説

建設業における帳簿管理は、事業の健全な運営に欠かせない重要な要素です。
帳簿の適切な保管は、法令遵守にもつながるからです。
また、建設業の帳票は、勘定項目や売上計上までの期間が長いなど、一般的な帳簿とは異なります。
この記事では、建設業における帳簿の基本的な特徴や保存期間、適切な保管方法を詳しく解説します。
建設業に従事する方や、帳簿管理の効率化を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
帳簿とは
帳簿とは、企業の経営活動や財務状況を記録し、管理するための書類です。
帳簿は、事業の収入や支出、資産や負債などの財務情報を体系的に整理し、経営判断や税務申告の根拠として利用されます。
また、帳簿にはさまざまな種類があり、目的に応じて作成されます。
帳簿の種類と目的をそれぞれ見ていきましょう。
帳簿の種類
帳簿にはいくつかの種類があります。
以下に、おもな帳簿名称と役割をまとめました。
| 帳簿名称 | 役割 |
| 仕訳帳 | すべての取引を日付順に「借方」と「貸方」に分けて記録する |
| 総勘定元帳 | 仕訳帳から転記した取引を勘定科目ごとに記録し、財務状況を詳細に把握する |
| 現金出納帳 | 現金の出入りを記録する |
| 預金出納帳 | 預金の管理に役立つ、銀行口座の取引を記録する |
| 買掛帳 | 仕入れ先ごとの取引を管理する(支払い状況を把握する) |
| 売掛帳 | 得意先ごとの売上取引を管理する(売掛金の管理に用いる) |
| 経費帳 | 経費の発生状況を記録する |
| 固定資産台帳 | 企業が保有する固定資産の状況を記録する |
これらの帳簿を適切に管理することで、企業の経営状態を正確に把握できます。
帳簿の目的
帳簿のおもな目的は、企業の経営状態を正確に把握し、効率的な経営判断を行うことです。
具体的な目的を以下にまとめました。
| 目的 | 詳細 |
| 経営判断の材料 | 収支や資産状況を分析し、経営戦略を立案する |
| 財務報告 | 決算書などの財務報告書を作成するための基礎データとして使用し、外部の利害関係者に対して企業の経営状況を報告する |
| 税務申告 | 税務署に対して正確な税務申告を行う |
| 内部統制 | 不正や誤りを防止し、経営の透明性を確保する |
帳簿の適切な管理と運用は、企業の健全な経営に欠かせません。
建設業の帳簿が一般的な帳簿と異なるポイント
業務の特性や取引の形態により、建設業の帳簿は一般的な企業の帳簿と異なります。
ここでは、3つの具体的なポイントを紹介します。
- 建設業ならではの帳票がある
- 建設業特有の勘定項目がある
- 売上計上までの期間が長い
それぞれ詳しく見ていきましょう。
建設業ならではの帳票がある
建設業では、工事に関する特有の帳票が必要です。
以下に、各帳票と目的をまとめました。
<建設業特有の帳票>
- 工事完了報告書
工事の完了を報告する(施工内容や完了日などを記載)
- 工事台帳
工事現場ごとの取引内容を記録し、原価を集計する(材料費や労務費、外注費などを含む)
- 工程表
工事の各工程にかかる日数や納期までのスケジュール、進捗状況などをまとめる
これらの帳票は、工事の進捗管理やコスト管理に欠かせないもので、一般的な企業では見られない特有のものです。
建設業特有の勘定項目がある
建設業では、工事の進行状況や費用の特性を反映させるような、特有の勘定項目が用いられます。以下に、各勘定項目と詳細をまとめました。
<建設業特有の勘定項目>
- 未成工事支出金
まだ完成していない工事にかかった費用を記録する。一般会計でいう「仕掛品」に相当する
- 完成工事原価
材料費・労務費・外注費・経費など、工事の完成に必要な費用を合算した金額。一般会計は「売上原価」に近い
- 工事未払金
品は受け取ったものの、支払いが完了していない金額を記録する。一般会計でいう「買掛金」に相当
- 未成工事受入金
まだ完成していない工事に対して受け取ったお金を記録する。一般会計でいう「前受金」に相当
これらの勘定項目は、工事の進行状況や収支を正確に把握するために必要です。
【関連記事】建設業における労務費とは?計算方法や人件費との違いを解説
売上計上までの期間が長い
建設業では、工事着手から完成までの期間が長いため、売上計上までに時間がかかります。
工事の完成引き渡し後に売上を計上するため、半年後や1年後に多額の売上金が計上されることがあります。
このため、材料費や労務費などの先行費用は発生しているものの、売上が計上されるまでの期間が長いため、資金繰りの管理が重要です。
また、出来高払いなどの契約によっては、工事の進捗に応じた部分的な売上計上も行われます。
建設業における帳簿の保存期間
建設業では、帳簿の保存期間が法令によって厳格に定められています。
これは、税務調査や経営の透明性を確保するために必要な措置です。
帳簿の保存期間は、おもに「法人税法」と「会社法」の規定に従わなければなりません。
法人税法では、一般的な帳簿や伝票は7年間の保存義務が定められています。
ただし、欠損金が発生した事業年度は、9年間または10年間の保存が必要です。
一方、会社法では、すべての帳簿を一律で10年間保存することが求められています。
そのため、建設業では、基本的に10年間の保存が推奨されます。これは、法人税法と会社法の両方の要件を満たすためです。
関連記事:見積書の保管期間はどのくらい?必要性や適切な保管方法について
各帳簿の保管方法
建設業の帳簿の保管方法は慎重に選択しなければなりません。ここでは、帳簿の保管方法を3つのポイントに絞って解説します。
- 電子による保管
- 紙による保管
- 電子帳簿保存法で電子見積書の印刷はNGに
それぞれ見ていきましょう。
電子による保管
電子による帳簿の保管は、法令で認められている方法です。
電子帳簿保存法に基づき、帳簿や伝票を電子データで保存することが推奨されています。
具体的な保管方法を以下にまとめました。
<保管方法>
- 電子帳簿保存
会計ソフトやERPシステムを使用して作成した帳簿を電子データのまま保存する
- スキャナ保存
紙の帳簿や伝票をスキャナで読み取り、画像データで保存する。適切な解像度や形式で保存する必要がある
- 電子取引データ保存
電子取引で受け取ったデータをそのまま電子データで保存する(見積書や請求書、領収書などが含まれる)
電子データの保管には、改ざん防止措置や適切なバックアップが必要です。
また、保存したデータは簡単に検索できることが求められます。
関連記事:【建設業向け】Excel帳票の作り方とは?メリット・デメリットも
紙による保管
紙による帳簿の保管は昔からある方法で、現在でも多くの企業で行われています。
ただし、紙媒体での保管方法は以下の点に注意が必要です。
<紙媒体による保管の注意点>
- ファイリングシステムの整備
帳簿や伝票を種類ごとに整理し、見やすく保管する
- 保管スペースの確保
物理的なスペースを確保し、効率的に管理する
- 環境条件の管理
紙は湿気や光によって劣化するため、保管環境を適切に保つ。温度や湿度の管理、直射日光を避けるなどの対策が求められる
紙による保管は、電力供給やシステム障害に依存しないため安定していますが、保管スペースや管理方法に気を付けましょう。
電子帳簿保存法で電子見積書の印刷はNGに
電子帳簿保存法の施行により、電子取引に関する帳簿類は電子データで保存することが義務付けられています。
具体的には、2024年1月以降、電子取引で受け取った見積書や請求書などの帳簿類は、紙に印刷して保存することが認められていません。
この法改正により、以下の対応が求められます。
<法改正に伴い必要な対応>
- 電子データの保存義務
電子取引に関するすべての帳簿類は、電子データのまま保存しなければならない。
適切なシステムを導入し、保存要件を満たす必要がある
- 改ざん防止措置
保存する電子データには、改ざん防止のための技術的対策が求められる。タイムスタンプの付与やアクセス制限などが必要
- データの検索性
保存した電子データを、迅速に検索できる状態が求められる
このように、電子帳簿保存法の施行により、企業は電子データの保管体制を強化する必要があります。
【関連記事】
電子帳簿保存法とは?建設業へのメリットや対象書類も解説
建設現場にペーパーレス化が必要な理由とは?メリットや導入のポイントも
帳簿の保管を電子化するメリットとデメリット
帳簿保管の電子化は多くの利点がありますが、一方でいくつかの課題も存在します。
ここでは、帳簿を電子化するメリットとデメリットを詳しく解説します。
メリット
帳簿の保管を電子化する大きなメリットは、物理的なスペースの節約です。
紙の帳簿を保管するには多くのスペースが必要ですが、電子データであればその必要がありません。
これにより、オフィスの保管スペースを有効に活用でき、ほかの用途への使用が可能です。
また、電子データはデジタルで管理されるため、必要な情報を迅速に検索できます。
これにより、業務効率が向上し、時間の節約にもつながります。
とくに大量の帳簿を管理する必要がある場合、検索機能の効率化は有益です。
さらに、紙の帳簿を印刷・郵送・保管するための費用が不要なため、企業の運営コストを削減できます。
紙媒体の管理にかかる人件費も削減されるため、全体的なコスト効率も上がるでしょう。
セキュリティの面でも、アクセス制限やバックアップが容易なため、情報の漏洩や紛失のリスク低減が可能です。
紙の使用を減らすことで、環境負荷を軽減でき、企業の社会的責任を果たせます。
これにより、エコフレンドリーな企業としてイメージ向上につなげられるでしょう。
デメリット
電子化にはシステムの導入やクラウドサービスの契約が必要で、初期費用が発生し、システムの設定やデータ移行にも時間と費用がかかります。
また、電子データはサイバー攻撃のリスクにさらされるため、適切なセキュリティ対策が必要です。
ファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入、定期的なセキュリティチェックが求められます。
さらに、新しいシステムの操作に慣れるまで時間がかかることがあります。
従業員への教育やトレーニングの労力と費用も考慮しなければなりません。
システム障害やデータ消失のリスクもあります。
システム障害が発生すると、業務が停止する可能性があり、データのバックアップ体制の整備が重要です。
災害対策も考慮し、万が一の事態に備える必要があります。
建設業の帳簿作成ソフトの選び方
帳票作成ソフトの選定にあたって、6つのポイントを解説します。
- 入力・操作は行いやすいか
- セキュリティ対策がされているか
- サポート体制は充実しているか
- 導入方法が自社に適しているか
- 必要な機能が揃っているか
- 予算と見合っている価格か
それぞれ見ていきましょう。
入力・操作は行いやすいか
ソフトが直感的で使いやすいインターフェースを持っているかどうか、日常的な入力作業がスムーズに行えるかを確認しましょう。
試用期間が設けられているソフトも多いので、実際に操作してみて、現場のスタッフが問題なく使えるかどうかを見極めることが重要です。
セキュリティ対策がされているか
建設業では、財務データや取引先情報など、機密性の高いデータを扱います。
そのため、帳簿作成ソフトには高度なセキュリティ対策が施されていることが必須要件です。
データの暗号化やアクセス制御、バックアップ機能などセキュリティ対策が十分にされているかを確認しましょう。
また、法令遵守の観点からも、電子帳簿保存法に対応しているかどうかもポイントです。
サポート体制は充実しているか
ソフトウェアの導入後の操作方法や不具合に関するサポートが充実していることも重要です。
サポート体制が整っていると、トラブルが発生した際に迅速に対応してもらえるため、業務の停滞を防げます。
電話やメールでのサポート、オンラインマニュアルやFAQの充実度もチェックポイントです。
導入方法が自社に適しているか
クラウド型やオンプレミス型など、帳簿作成ソフトの導入にはさまざまな形態があります。
自社のIT環境や業務フローに適した導入方法を選びましょう。
たとえば、クラウド型は初期費用が低く、場所を問わず利用できる利便性がありますが、インターネット環境に依存します。
一方、オンプレミス型は高いセキュリティを確保できますが、初期費用が高くなる傾向があります。
必要な機能が揃っているか
建設業特有の帳簿作成や管理機能が揃っていることも重要です。
たとえば、工事ごとの原価管理や進捗管理、複数のプロジェクトを一元管理できる機能など、自社の業務に必要な機能が備わっているか確認しましょう。
また、ほかの会計ソフトや業務システムとの連携可否も業務効率化に直結するポイントです。
予算と見合っている価格か
初期費用だけでなく、運用にかかるランニングコストも考慮する必要があります。
価格が高すぎると、導入後のコスト負担が大きくなり、運用が難しくなる可能性があるからです。
一方、安価なソフトは必要な機能やサポートが不足していることがあるため、バランスを見極めることが重要です。
建設業に特化した帳票作成ならアドバンの「Neoシリーズ」
株式会社アドバンが提供する「Neoシリーズ」は、建設業に特化した帳票作成ソフトとして多くの企業に支持されています。
このシリーズは、積算から見積作成、原価管理まで一気通貫で対応できるため、業務全体の効率を大幅に向上させます。
「Neoシリーズ」は、Excel感覚の簡単な操作感のため、特別なスキルがなくてもすぐに使いこなすことが可能です。
本格的な機能も備えているため、業務の正確性と効率を両立させられます。
また、アドバンの製品同士はシームレスに連携可能です。
各ソフトを組み合わせて使用することで、さらに業務効率を高められます。
さらに、アドバンは操作の相談を回数無制限で受け付けていることが強みです。
これにより、他社の建設ソフトを使いこなせずに導入を断念した企業様でも、安心して導入できます。
導入後のサポートも充実しており、リアルタイムでのリモートサポートが受けられるため、トラブルが発生した際にも迅速に対応してもらえます。
帳票作成ソフトの導入を検討中の方は、アドバンの「Neoシリーズ」を候補としてみてはいかがでしょうか。
興味のある方は、お気軽にこちらからお問い合わせください。
建築見積ソフト「Kensuke NEO」の導入事例

ここでは、建築見積ソフト「Kensuke NEO」を導入した企業の事例について見てみましょう。
株式会社山上組様の導入事例
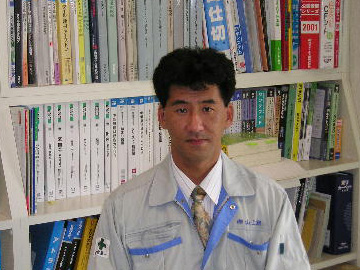
山上組様では、積算作業の効率化と属人化が課題でした。Kensuke NEOを導入した結果、誰でも短期間で習得可能な操作性と、柔軟なシステムの使いやすさに驚きました。
導入後は手作業に比べて5〜10倍の効率化を実現し、アフターサポートの充実も高く評価されています。
株式会社ナカシロ様の導入事例

ナカシロ様は、積算業務の手間を軽減するためにKensuke NEOを導入しました。2ヶ月間の試用期間中に、実物件を使用してソフトをテストし、操作方法をマスター。
建築部員の全員が操作できる体制を整えています。
石坂建設株式会社様の導入事例

石坂建設様では、従来の手作業による積算が業務に支障をきたしていました。Kensuke NEOの導入により、作業効率が大幅に向上し、見積の作成に十分な余裕が生まれました。
導入以来、効率的な積算が可能となり、今では欠かせないツールとなっています。
建設業の帳票は法改正に合わせた形式が求められる
ここまで、建設業における帳簿管理や保存方法、帳簿作成ソフトの選び方を詳しく解説してきました。
建設業はほかの業種と異なり、特有の帳票や勘定項目が多く、帳簿の保存期間や保管方法は、法令に基づいた厳格な管理が求められます。
その中で、とくに重要なのが法改正に対応した帳票の形式です。
建設業の帳票は、法人税法や電子帳簿保存法など、法令の改正に伴って形式や保存方法が変わることがあります。
法改正に迅速に対応するためには、最新の法令に準拠した帳票作成が不可欠です。
ぜひ、自社に合った方法で、法令に基づいた正確な帳簿管理を実践しましょう。
【アドバンが提供するサービス一覧】
- 建築見積ソフト「Kensuke Neo」
- 仕上積算ソフト「Neo仕上」
- 工事原価計算ソフト「Neo原価」
- RC躯体積算ソフト「松助くん」
- 作業日報管理ソフト「Neo日報」
- ワークフロー管理ソフト「ネオ ワーク」

株式会社アドバン代表取締役社長
「建設関連ソフトを通して世の中に貢献する」がモットーです。
創業から20年以上、重要な業務である積算や見積書作成などの効率化・高精度化に貢献したいとの思いで、建設業に特化したシステムの開発に取り組んできました。
すべてのソフトで無料で使用評価をいただくことが可能であり、ほとんどのお客様に十分納得をいただいたうえで、システムを導入していただいています。