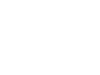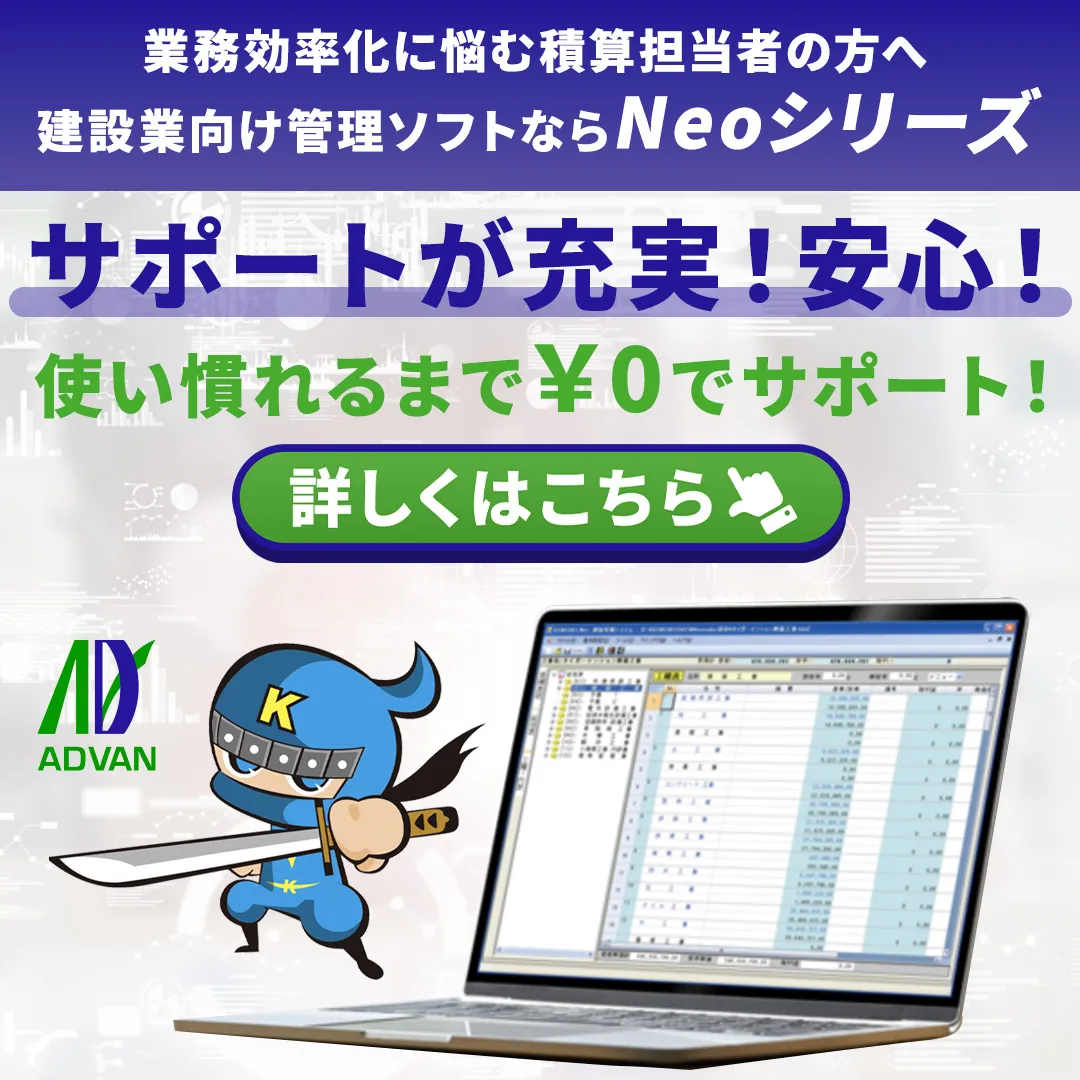見積書の保管期間はどのくらい?必要性や適切な保管方法について

見積書には法律で定められた保管期間があり、適切な管理が求められます。取引の証拠に欠かせない書類として認識されるためです。
しかし、必要性や保管方法を把握している方は多くいません。
この記事では、見積書の保管期間について詳しく解説します。
法人と個人事業主で異なる点や、電子データと紙の見積書の取り扱いの違いなどを理解したい方も、ぜひ参考にしてください。
見積書に保管期間が決められている理由
見積書の保管期間が定められている理由は、4つあります。
| 理由 | 説明 |
| 法的要件の遵守 | 法人税法や所得税法により、一定期間の保存が義務付けられています。税務調査や会計監査の際に必要となります。 |
| トラブル防止と証拠保全 | 取引内容や金額の確認に使用され、後々のトラブル防止に役立ちます。取引先との齟齬が生じた場合の重要な証拠となります。 |
| 経営分析と予算策定 | 過去の見積書を参照することで、価格設定の妥当性や取引の傾向を把握できます。これにより、より適切な経営判断が可能になります。 |
| 電子化への対応 | 電子帳簿保存法の改正により、電子データでの保存が義務化されました。紙と電子の両方について、適切な保管が求められるようになりました。 |
企業の健全な運営と発展には、見積書の適切な保管が欠かせません。法令遵守をはじめ、経営戦略にも影響を与えます。
見積書の保管期間
見積書の保管期間は、法人と個人で異なります。
| 区分 | 基本保管期間 | 特殊なケース |
| 法人 | 7年間 | ・欠損金がある場合:10年間
・税務調査中や訴訟の可能性がある場合:7年以上 |
| 個人 | 5年間 | ・消費税の課税事業者:7年間
・青色申告者:7年間(推奨) |
それぞれの期間を詳しく解説します。
法人の場合
法人の見積書の保管期間は、原則として7年間です。期間は法人税法に基づいて設定されています。
ただし、欠損金が生じた事業年度の場合は、繰越控除制度に対応するため、保管期間が10年間に延長されます。
また、税務調査の対象になっている、訴訟に関わる可能性がある場合は、7年を超えた保管が推奨されます。
さらに、電子帳簿保存法の改正により、電子データで受け取った見積書は、データのまま保存しなければいけません。
法令遵守と共に、自社の事業状況を考慮した適切な期間の設定が求められるでしょう。
【関連記事】
建設現場にペーパーレス化が必要な理由とは?メリットや導入のポイントも
電子帳簿保存法とは?建設業へのメリットや対象書類も解説
個人の場合
個人事業主の見積書の保管期間は、原則として5年間です。期間は所得税法に基づいて定められています。
ただし、消費税の課税事業者の場合は、消費税法に基づき7年間の保管が必要です。適用されるのは、前々年の課税売上高が1,000万円を超える事業者です。
また、青色申告の場合も、特別控除の適用を受けるために7年間の保管が推奨されます。
加えて、電子帳簿保存法の改正により、電子データで受け取った見積書は、電子データのまま保存しなければいけません。
事業状況を正確に把握し、適切な期間を設定しましょう。
見積書の適切な保管方法
見積書の適切な保管方法は、電子と紙で異なります。
| 保管方法 | 電子見積書 | 紙の見積書 |
| 保存形式 | 電子データのまま(PDF、XMLなど) | 原本をそのまま |
| 保管場所 | サーバーまたはクラウド(日本国内) | 湿気や直射日光を避けた場所 |
| 改ざん防止 | タイムスタンプ付与または訂正削除履歴の保持 | 専用キャビネットや保管庫の使用 |
| 検索性 | 検索機能の実装 | 日付順や取引先別の整理、インデックス付け |
| バックアップ | 定期的なバックアップ | スキャンしてデータ保存(原本保管も必要) |
| 法令対応 | 電子帳簿保存法に準拠 | 法定保存期間の遵守 |
適切な保管は法令遵守だけでなく、業務効率の向上につながります。それぞれの保管方法を詳しく見ていきましょう。
電子見積書の場合
電子見積書の保管方法は、電子帳簿保存法に基づいて適切に行わなければいけません。保存は電子データのまま行う必要があり、紙に印刷して保管するだけでは不十分です。
また、保存する電子データは、改ざん防止措置を施す必要があります。タイムスタンプを付与するか、訂正削除履歴を残す仕組みを導入するのが一般的です。
加えて、以下の保管も欠かせません。
- 検索機能の実装
- 国税庁が認めた保存形式(PDFやXMLなど)の使用
- バックアップを定期的に取る
真正性の確保には、電子署名の付与が最適です。保存場所は、自社のサーバーでもクラウドサービスでも構いません。ただし、日本国内に保存する必要があります。
要件を満たせば、電子見積書を適切に保管できます。
【関連記事】建築業の見積作成に活用できるフリーソフト3選と有料ソフト3選
紙の見積書の場合
紙の見積書は、原本をそのまま保管するのが基本です。コピーや写しではなく、実際に受け取った紙の見積書を保管しなければいけません。
保管場所は直射日光を避け、温度や湿度の変化が少ない環境が最適です。専用のキャビネットや保管庫を使用するといいでしょう。
整理方法は、日付順や取引先別など、検索しやすい方法を選びます。ファイリングシステムを導入し、インデックスを付ければ、必要な時にすぐに取り出せます。
また、こまめにチェックする習慣を作りましょう。虫食いや劣化がないか、年に1回は確認するのが望ましいです。必要に応じて、中性紙の封筒やファイルに入れ替えるなどの対策を取ってください。
なお、紙の見積書をスキャンしてデータとしても保存しておくと、バックアップに役立ちます。
電子帳簿保存法で電子見積書の印刷はNGに
2022年1月に施行された電子帳簿保存法の改正により、電子見積書を印刷して紙で保存する行為が認められなくなりました。
改正後のおもな変更点は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 保存方法 | 電子データのまま保存が必須 |
| 施行日 | 2022年1月1日 |
| 移行期間 | 2023年12月31日まで |
| 対象 | メール、クラウドサービスで受け取った見積書など |
| 主な目的 | データの改ざんリスク低減、真正性確保 |
改正の目的は、デジタル化の推進と情報における真正性の確保です。電子データのまま保存すると、検索性や保管効率が向上し、経営の効率化につながります。
移行期間はすでに終了しているため、今後は電子保存のための体制を整えていかなければいけません。特に、企業はコンプライアンスを維持しつつ、業務の効率化を図る必要があるでしょう。
見積書は電子作成が便利
見積書の電子作成は、業務効率化と正確性の向上の両面にメリットをもたらします。
| メリット | 具体例 |
| 時間短縮 | テンプレート使用で作成時間を大幅に短縮 |
| 正確性向上 | 自動計算機能により人為的ミスを防止 |
| 検索性 | 過去の見積書を瞬時に検索・参照可能 |
| コスト削減 | 紙や印刷費用の削減 |
| 環境配慮 | 紙の使用量削減で環境負荷を低減 |
| 法令対応 | 電子帳簿保存法への対応が容易 |
| データ連携 | 他のシステムとの連携が簡単 |
電子作成を導入すれば、見積書の管理や修正にかかる手間を省けます。クラウドを活用すると、安全な保存ができるほか、場所を選ばずアクセスできるでしょう。
関連記事:建築業に取り入れたいクラウドサービスとは?メリットも解説
建築用の見積書作成なら「Kensuke Neo」
建築用の見積書作成ソフトKensuke Neoは、エクセルのように直感的な操作ができます。リフォームから大規模工事まで幅広く対応し、JW_CADのデータから積算結果をすぐに転送可能です。
また、アドバン製品間の連携により、積算から見積までをスムーズに行えます。
7階層までの内訳作成や、柔軟な書式カスタマイズにも対応しているほか、操作に関する相談を回数無制限で利用できます。
したがって、建設ソフトを使いこなせず諦めてしまった企業でも安心して導入できます。
見積書の作成を効率化させたいなら、Kensuke Neoがおすすめです。
建築見積ソフト「Kensuke NEO」の導入事例

ここでは、建築見積ソフト「Kensuke NEO」を導入した企業の事例について見てみましょう。
株式会社山上組様の導入事例
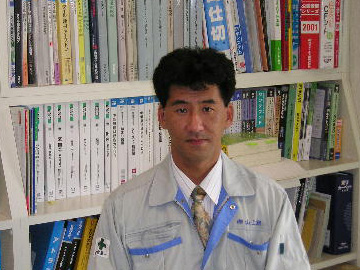
山上組様では、積算作業の効率化と属人化が課題でした。Kensuke NEOを導入した結果、誰でも短期間で習得可能な操作性と、柔軟なシステムの使いやすさに驚きました。
導入後は手作業に比べて5〜10倍の効率化を実現し、アフターサポートの充実も高く評価されています。
株式会社ナカシロ様の導入事例

ナカシロ様は、積算業務の手間を軽減するためにKensuke NEOを導入しました。2ヶ月間の試用期間中に、実物件を使用してソフトをテストし、操作方法をマスター。
建築部員の全員が操作できる体制を整えています。
石坂建設株式会社様の導入事例

石坂建設様では、従来の手作業による積算が業務に支障をきたしていました。Kensuke NEOの導入により、作業効率が大幅に向上し、見積の作成に十分な余裕が生まれました。
導入以来、効率的な積算が可能となり、今では欠かせないツールとなっています。
見積書の保管期間を守り適切な方法で管理しよう
見積書の保管期間は、法人で原則7年間、個人事業主で原則5年間です。ただし、状況に応じて柔軟な対応が求められます。
また、電子見積書は電子データのまま保存し、紙の見積書は適切な環境で原本を保管しましょう。
電子帳簿保存法の改正により、電子データの印刷保存ができなくなった点にも注意が必要です。
適切な見積書の管理は、法令遵守以上の価値があります。経営における透明性の向上や、業務効率化につながるでしょう。
自社の見積書管理方法を見直し、必要に応じて改善を検討してください。
【アドバンが提供するサービス一覧】
- 建築見積ソフト「Kensuke Neo」
- 仕上積算ソフト「Neo仕上」
- 工事原価計算ソフト「Neo原価」
- RC躯体積算ソフト「松助くん」
- 作業日報管理ソフト「Neo日報」
- ワークフロー管理ソフト「ネオ ワーク」

株式会社アドバン代表取締役社長
「建設関連ソフトを通して世の中に貢献する」がモットーです。
創業から20年以上、重要な業務である積算や見積書作成などの効率化・高精度化に貢献したいとの思いで、建設業に特化したシステムの開発に取り組んできました。
すべてのソフトで無料で使用評価をいただくことが可能であり、ほとんどのお客様に十分納得をいただいたうえで、システムを導入していただいています。